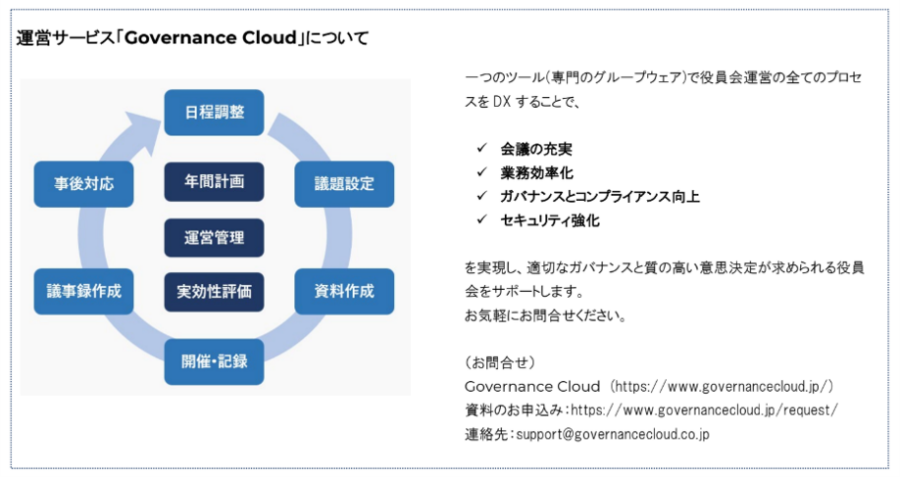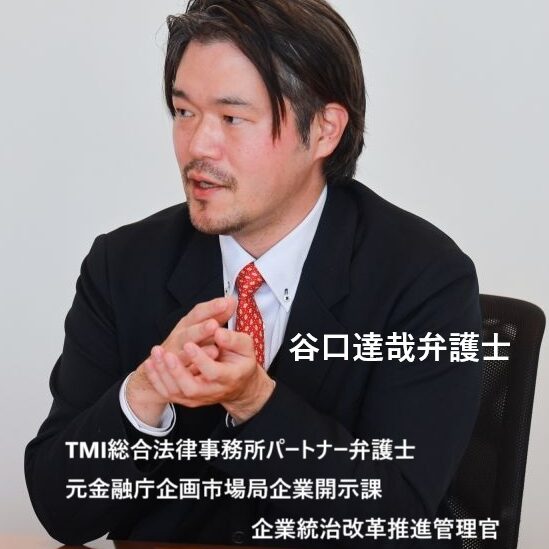TMI 総合法律事務所の弁護士・谷口氏は、2012年と2022年の2回にわたり金融庁に出向し、日本のコーポレートガバナンス改革の現場で実務に携わり、制度設計に関わっています。その谷口氏にガバナンスコード策定主体の立場で、「日本のコーポレートガバナンス改革のこれから」についてお話を伺いました。本記事はその後編です。
・ご経歴
2008年 3月 中央大学法学部法律学科卒業
2008年 4月 最高裁判所司法研修所入所
2009年 9月 東京弁護士会登録
TMI 総合法律事務所勤務
2012年 7月 金融庁総務企画局企業開示課勤務
2015年 4月 TMI 総合法律事務所復帰
2017年 1月 パートナー就任
2022年 7月 金融庁企画市場局企業開示課
企業統治改革推進管理官
2024年 4月 TMI 総合法律事務所復帰
ご経歴
・2008年 3月 中央大学法学部法律学科卒業
・2008年 4月 最高裁判所司法研修所入所
・2009年 9月 東京弁護士会登録
TMI 総合法律事務所勤務
・2012年 7月 金融庁総務企画局企業開示課勤務
・2015年 4月 TMI 総合法律事務所復帰
・2017年 1月 パートナー就任
・2022年 7月 金融庁企画市場局企業開示課
企業統治改革推進管理官
・2024年 4月 TMI 総合法律事務所復帰

・インタビュアー
ガバナンスクラウド株式会社
代表取締役 上村はじめ
1999年センチュリー監査法人(現あずさ監査法人)入所。
監査、フィナンシャルアドバイザリーに従事 2004年(株)カカクコム入社。経営企画、IR、コーポレートガバナンス業務を担い2009年取締役としてコーポレート部門責任者を務める 2020年 コーポレートガバナンス・財務コンサルティング事業を開始。2021年 6月 ガバナンスクラウド(株)設立。
上場企業、海外企業含む多数の社外役員経験あり。公認会計士。
取締役会の実効性向上と社外役員の役割
上村「ありがとうございます。ここから少し踏み込んだご質問をさせていただきたいと思います。取締役会の実効性向上に関して、先ほど「社外役員の活用が重要」というお話がありました。日本に限らず、海外でも役員会のガバナンスの中心は社外役員が担っていますが、社外役員比率は過半数というケースが多いです。一方、日本はプライム上場企業でさえ社外役員の割合は通常1/3程度、過半数という企業は約20%という状況でガバナンスは機能しないのではないか、また欧米並みの機能を日本の社外役員に求めるのは酷ではないのかという声もありますが、この点どのような議論がなされているのでしょうか?」

谷口氏「そうですね。考え方としては、やはり「質」が重要です。先ほどおっしゃったように、社外役員の負担が重いのは、求められる能力や資質が非常に高度なものだからです。経営を監督する立場として、高い専門性や経験が必要であり、それに適した人材は決して多くありません。
しかし、人材の成長には時間がかかるものですから、現時点で十分な人材が揃っていないのは、ある意味しょうがないことです。
このような状況で、仮に社外役員の過半数を義務付けるとどうなるでしょうか。能力が不足している人材を無理に増やすだけになり、結果的に質の低下を招く可能性があります。本来、ガバナンスの目的は「社外役員の数を増やすこと」ではなく、「適切な人材による実効性のある監督機能を確立すること」です。
もし「過半数を目指すこと」がゴールなら、すぐにコードを改訂して実現することも可能です。しかし、それで本当にコーポレートガバナンス改革の目的は達成されるでしょうか? 現状、1/3ですら適任者が不足していると言われている中で、数を増やすことが解決策にはならないでしょう。まずは、ガバナンスに必要な素養を持つ人材が増えていくことが重要であり、それを待ってから次のステップに進むべきだ、というのがアクションプログラムの基本的な考え方です。
ただ、やはり「過半数」という期待は投資家の間で非常に強いですが、それが本当に正しい方向性なのかどうかは、もっと慎重に検証する必要があると思っています。
もし社外取締役が1/3の状態では十分に機能せず、その原因が1/3では足りないからだというのであれば、次のステップとして「過半数」を目指すのは理にかなっているとも言えます。ただ、それを前提として決めるのではなく、本当に必要なのかどうかをしっかり議論することが大切ではないでしょうか。」
上村「社外役員が少数派だから個々に求められる能力が高まるという面はないでしょうか?もし過半数が社外取締役であれば、個々のスキルがそこまで高くなかったとしても、例えば決議を止めるなど、牽制機能が高まると思います。」
谷口氏「大前提として、コーポレートガバナンス・コードは「ビジネスにストップをかけること」を期待しているわけではありません。社外取締役が「ビジネスにストップをかけること」が求められている役割だと考えているのなら、それは問題です。
本来、コーポレートガバナンス・コードの目的は、経営陣の適切なリスクテイクを促すことにあります。例えば、「資本コストはこれくらいで、株主はもっと高いリターンを求めているのに、現状ではそれを達成できていない。だから、よりリターンを高めるために、どのような成長投資をすべきか」といった議論をすることが求められます。
一方で、「この事業はリスクが高いからやめましょう」と判断するのは、むしろ監査の役割です。社外取締役がそこまで踏み込んでしまうと、コーポレートガバナンス・コードの本来の目的から逸れてしまう可能性があります。
ビジネスの細部で社外取締役が強い決定権を持つことは、必ずしも健全ではないと考えています。社外取締役は必ずしもその会社のビジネスに深い知識を持っているわけではなく、特別な見識や経験を持つ場合を除き、ビジネスの細部について最終判断を下すことは適切ではありません。
一方で、社外取締役が持つべき最大の権限は経営者交代の決定だと考えています。これはフォローアップ会議でもたびたび議論されていますが、「現在の経営が株主の期待に応えられない」と判断した場合、新たな経営者に交代させるべきだという考え方です。もっとも、実際に経営者の交代を行うことは極めて困難ですから、「抜かずの宝刀」と言えるでしょう。
その意味では、指名委員会の構成について過半数の独立社外取締役を求めるという議論は健全ですが、取締役会全体について過半数の独立社外取締役を求めるというのは何のためなのか現状判然としません。」
上村「もちろんビジネスに過剰な牽制がされるのは問題です。この点に関連して、役員会で扱う議題が執行に寄りすぎているのではないかという論点もあります。
欧米型のガバナンスは、過半数はもちろん、CEO以外は全員社外という形で運営されているのが通常で、社外役員が事業の詳細に精通していなくても、取締役会の議論が戦略やリスク、大きな方向性が中心で、個々の執行は経営陣に委任しているために、機能していると言われます。
お話を伺っていて、そのような姿が日本企業にも求められているのではないかと感じましたがいかがでしょうか?現在の法体系でもそういった対応は可能ですよね。」

谷口氏「取締役会の承認が必要な議案が増えてしまう理由は、監査等委員会や指名委員会設置会社では委任が広くできる一方、監査役会設置会社では委任が制限されているからです。このため、法令を遵守するためには議案が増えてしまうという現実があります。
ガバナンスコードの最初の策定時から、取締役会の役割は大きな戦略や方向性を示すことだと明記されており、細かな部分まで取締役会が関与することを期待していませんでした。
そのため、委任を拡大していく方向に進んでいくのは自然な流れだと思います。実際、監査役会設置会社ではなく、監査等委員会設置会社に移行していく企業も多いです。
指名委員会等設置会社が理論的には美しい形です。ただし、現実的には、いくつか問題点も指摘されているように、さらにブラッシュアップが必要だと思います。」
上村「社外役員が重要という点を強調されていらっしゃいますが、監督の役割は社外だけでなく業務執行取締役も負っていますよね。例えば、経産省や金融庁が共同で公表した『社外役員ことはじめ』というガイドラインには、社外役員としての姿勢や責務について書かれていますが、業務執行取締役にも同じような責任が求められると思いますが、その点はいかがでしょうか?」
谷口氏「確かに会社法上は、全取締役に監視義務があり、ガバナンスコードにも取締役会が監督するべきだと記載されています。これはその通りだと思います。しかし、実際にそれを期待できるかどうかという点が問題です。例えば、『うちは専務の業務を部下の常務が監督している』と言ったところで、誰がそれを信じるのでしょうか?同じ人事ラインに乗っている方々が相互に監督しあうというのは現実的ではありません。だからこそ、社外取締役が必要だということです。社外取締役は、投資家の立場から見ると、この人物であれば忌憚なく監督してくれるだろうという信頼が寄せられる存在でなければなりません。
専務や常務などの業務執行取締役は、監視義務を負うとしても、自分の担当する部署を持ち、その部署のトップであるという役割が強いため、自分の所管していない部分にはなかなかタッチできません。会社法でも信頼の原則が認められており、自分が関与していない部分について、関与している取締役と同等の責任を負うわけではないとされています。こうした枠組みの中で、業務執行取締役に全ての監督を期待して、さらに投資家に『安心して投資してください』というメッセージを送ることは、響かないだろうなと思います。」
上村「そうですね。その観点から取締役会の性質として、現在日本ではマネジメントボードが主流ですが、今後モニタリングボードに移行していくという考えはあるのでしょうか?もし将来的にモニタリングボードに移行すべきだとすれば、人事の考え方も含めかなり大きな変革が必要だと思います。」
谷口氏「おそらく、モニタリングボードを目指しているわけではないと思います。確かにモニタリングボードへの憧れはあるかもしれませんが、それを実現しようという全員の意識があるかというと、必ずしもそうではないと感じます。もちろん、それぞれの考えがあると思いますが、モニタリングボードが絶対に優れているという確固たる証拠がない限り、必ずしもその方向に進むべきだとは言い切れないのではないでしょうか。
結局、みんな悩みながら進んでいると思います。ただし、モニタリングボードとマネジメントボードの二つのアプローチが存在しているという認識は共有されていると思います。どちらに進むべきかについては、まだ決めかねているというのが実情でしょう。モニタリングボードにしても、形式的な話だけでは意味がないというのは明確に感じています。実際、モニタリングボードを採用していたけれどうまくいかなかったという企業もあり、形式だけではうまくいかないことがあるということを、多くの方が実感していると思います。」
上村「ありがとうございます。実態に即した判断が必要ということですね。話は変わりますが、2023年3月に東証から資本コストや株価を意識した経営の要請がなされ、経済界にかなりインパクトがあったと思います。特にPBR(株価純資産倍率)が1倍を下回る約半数の企業は対応に追われています。この状況をどのように捉えているか、お聞かせいただけますか?」
谷口氏「東証の要請はルールの改正ではなく、あくまで企業へのお願いにすぎなかったにも関わらず、メディアや社会での反響が非常に大きかったという点は驚きでした。このような取り組みが大きなインパクトを生んだ背景には、ガバナンスや企業価値向上に対する社会の関心の高まりもあるのでしょう。ルールの改正に縛られず、啓蒙活動や他のアプローチで影響を与えられることの重要性も実感されたのではないでしょうか。
その一方で、メディアの注目が PBR に集まりすぎたのは少し残念でした。市場株価は様々な期待や憶測によって変動しますから、そこにフォーカスされてしまうと企業側としても何をすればいいのかわからなくなると思います。もっと企業としての本質的な価値向上や成長性に注目してほしかったですね。
実際、2023 年 4 月のアクションプログラムにはあえて「株価」という言葉を入れていません。「株価」という言葉を入れると、みんなその方向に引きずられてしまうおそれがあり、中長期的な企業価値向上という考え方から逸れてしまうおそれがあるという指摘があったためです。
そうであるとしても、東証がここまで踏み込んだ取り組みをしたことには、本当に驚きました。PBR に関する誤解を招いた部分はあったものの、それでもその影響を大きく上回る効果があったと思います。全体として、非常に良い施策だったのではないかと思っています。」
コーポレートガバナンスの現在地と未来
上村「ありがとうございます。コーポレートガバナンス関連で、今後のルール改正や動向について予想されていることはありますか?」
谷口氏「スチュワードシップコードの改訂については、現在まさに議論中で、そろそろ結論が出るのではないかと思います。
ガバナンスコードに関しては、必ずしもガバナンスそのものだけではありませんが、経産省の企業買収指針など、やはりこれらもガバナンスに関連する議論に繋がるため、今後かなり実務は影響を受けることになると考えています。」
また、資本コストについては、同様の発想に基づく新たな動きが出てきてもおかしくないと思っています。ただ、資本コストに関しては、結果として、例えば ROE がいくらか、資本コストがどうだったかという議論に偏ってしまうことが多いため、今後はその背景や解決策についてもう少し深掘りしていく方向になるのではないかと考えています。
上村「ありがとうございます。まだお伺いしたいことがたくさんあるのですが、一旦総括としてご意見を伺いたいと思います。日本のコーポレートガバナンス改革のゴールは何か、どこを目指しているのかについて教えていただけますか?先程お話しされた中長期的な企業価値の向上がその一つかもしれませんが、今その目標に向けてどの程度進んでいるとお考えでしょうか?」
谷口氏「ゴールについてどうすべきかという話ですが、政府としては中長期的な企業価値の向上を目指していると謳っています。政府としてはそうだろうと思いますが、個人的には、もうそろそろその目標設定は限界に来ているのではないかと感じています。コーポレートガバナンスの充実が業績や企業価値に直接結びつくというのは、コード策定当時は画期的な発想でしたが、今となって見てみると少し無理があるのではないかと思っています。もちろん、コーポレートガバナンスの強化が役立つ場面もありますが、必ずしも企業価値の向上と相関するわけではないと実感しつつあります。
その上で、私としては企業価値向上というゴールを少し修正すべき時期に来ていると思っていて、私はゴールを、投資家が安心して投資できる環境を整えることに設定することが適切だと考えています。
その点についてはかなり達成できていると感じており、もし「何合目か?」と聞かれたら、もう七合目か八合目くらいまで来ているのではないかと思っています。
もちろん、投資家からの指摘や不祥事が起きるたびに「日本のガバナンスはダメだ」と言われることもありますが、海外でも不祥事はよく起きています。1 つのミスを持ち出して日本のガバナンス全体がダメだと言われるのはおかしな議論です。問題はあくまで個別のケースであり、制度全体の問題ではありません。日本のガバナンス制度は、全体としては安心感のある状態になってきています。
個別の事例については解決しなければなりませんが、例えば裁判で会社側が株主側に負けることもあります。しかし、裁判を通じて問題が解決されているわけですから、それ自体は何ら悪いことではありません。裁判でどちらかが勝つのは当然のことですから、裁判で負けたからといって制度全体に大きな問題があるというのは飛躍だと思います。
裁判に行ったり、企業と株主の言い争いが起きたり、株主間の争いが生じたりというような事例があることも含めて、そうした議論が活発化されていること自体が成果といえますから、制度全体としてはかなり前進していると感じています。」
上村「とはいえ、グローバル投資家からはさらにガバナンスの強化を求める声があると思いますが、今後そちらにシフトしていく可能性はあるのでしょうか。確かに、中長期的な企業価値向上に直結するかは不確かとしても、ガバナンスとしてはグローバル投資家が求める水準を目指すということはあるのでしょうか?」
谷口氏「そうですね、それはまさに私が言ったように、「安心して投資できる環境」を目指すのであれば、海外の投資家にとっても、それが実現されるべきだということになり、その方向にシフトすることは十分あり得ると思います。
ただ、海外の投資家の不満をそのまま制度に組み込むことには慎重であるべきです。不満を言っている投資家は、すでに日本の企業やマーケットに投資しているわけでして、その上で、こうあるべきだという意見があるのは、非常に健全なことです。
問題だという指摘があることが問題なのではなく、そうした指摘も踏まえて企業や株主の間の議論が発展していくことが健全な世界だと思います。『あなたの会社の取締役会は独立性が足りない』という議論が出て、その議論を受けて経営者と株主が議論して、市場全体で判断していく、これこそがコーポレートガバナンス・コードが目指していた本来の姿です。
金融庁にいると、海外の投資家からたくさんの意見が寄せられます。海外の投資家はオブラートに包まず言いたいことをバンバン言ってくるのですが、それは議論として健全なことです。そのうえで企業側の事情もあって成り立っており、制度としては機能しているのではないかと思っています。」
上村「ありがとうございます。投資家と企業がぶつかり合うからこそ全体最適が果たされるということですね。先ほどガバナンスコードの経済界へのインパクトが想定以上だったというお話がありましたが、大きなインパクトを与えた要因をどのようにお考えかお聞かせいただけますか?」
谷口氏「やはり、わかりやすかったという点が大きな要因だったと思います。CG コードは平易な言葉で書かれており、英語も含めて、最初、法律家としては『こんなふわっとした表現で本当にワークするのか』と疑問に思う部分もありました。しかし、結果的にそれがわかりやすさに繋がり、非常に効果があったと感じています。
プリンシプルベースという考え方も、イギリスを参考にして提案されたものですが、このアプローチがすごく効果的だということを実感しまた。CG コード策定当時、本当に深夜までみんなで何度も何度も細かい文言や表現を修正して、完成させていったことを今でも覚えています。」
上村「こだわらなければならなかったのは、利害関係者が非常に多かったため、それぞれの立場や意見を反映させ、皆さんに受け入れられる形にする必要があったためとお察しします。
また、金融庁の方々の調整が大変だったという話がありましたが、そういった方々の調整が大きく貢献したのでしょうか?」
谷口氏「結局のところ、投資家と経済団体の双方がそれぞれ自由に意見を述べる中で、ガバナンスコードに関しては、特に経済界の譲歩が大きかったと感じています。むしろ、あそこまで経済界を納得させたこと自体が驚きです。その背景には、強い情熱や交渉の巧みさがあったのだろうと思います。私はその現場に立ち会っていないため詳細は分かりませんが、一体どのような手法で合意に至ったのか、改めて興味を持ちますね。」
上村「一人一人の働きが全体に大きな影響を与えることがあるのですね。これからの日本のコーポレートガバナンス改革に期待されることをお伺いできますでしょうか?」
谷口氏「そうですね。ガバナンスの観点で言うと、やはり根強く感じるのが、ショートターミズム(短期志向)の課題が依然として解決されていない点です。
年金基金やパッシブ運用のインデックスファンドなどは短期的な視点ではなく、長期的に投資を考えています。しかし一方で、昨今のアクティビストやヘッジファンド系の動きは、どうしてもショートターミズムに傾きがちです。
最近では、そうした動きがあたかも良いことのようにメディアで取り上げられることもあり、不満を抱えた株主が SNS などで同調する傾向がありますが、その効果が本当に市場全体にとってプラスなのかは疑問が残ります。例えば、日経の記事で「アクティビストが介入した企業の株価上昇は、平均して 1 年半程度しか持続しない」という分析がありましたが、まさにその懸念を表しています。
こうした状況が、日本の市場にとって本当に良いことなのか、改めて考える必要があるのではないでしょうか。」
上村「今は、ガバナンスコードのようなスタンダードがある中で、その基準に足りていないと考える企業の株をアクティビストが取得し、企業のガバナンス改善によるのか株が買い占めているからかは分かりませんが、実際に株価が上昇しているケースが見られます。こうした状況はどのようにとらえていらっしゃいますか?」
谷口氏「こうした状況は、今後なくしていかなければならないと考えています。実は、現在のガバナンス・コードやスチュワードシップ・コードでは、この問題への具体的な対応がほとんどなされていません。ショートターミズムに対する懸念はあるものの、「中長期的であるべき」と謳われているだけで、実際の対策には踏み込めていないのが現状です。そろそろ本格的にこの課題について考えていく必要があると感じています。
近いうちに、このテーマについて論文を書こうと思っていますが、私自身、金融庁時代に実現できなかった課題でもあります。それは「株主側の行動規範」をしっかりと考える必要がある、ということです。
スチュワードシップ・コードは、エンゲージメントに消極的な機関投資家に対して「もっと積極的にエンゲージメントせよ」と求めるものですが、逆に、過度なエンゲージメントを行う株主に対して「もっと抑制すべき」とするルールは存在しません。
たとえばアメリカでは、虚偽情報を流布するような行為は「風説の流布」として厳しく取り締まられます。即座に当局が動き、著名な人物ですら摘発されたことがあります。しかし、日本ではこうした行為が野放しになっており、それに便乗する動きが増えつつあります。これはまさにショートターミズム(短期志向)の極みといえる状況です。
この点について、そろそろ本格的に議論を深める必要があると感じています。」
上村「現状、日本はその点のルールが十分ではないとお考えなのですか?」
谷口氏「日本にも「風説の流布」に関するルールは存在するので、もしかすると問題は法律の不備ではなく、その執行にあるのかもしれません。ただ、少なくともガイドライン的な形で注意喚起を行うことは有効だと考えます。
実際、私が金融庁に入る前に策定されたガイドラインでは、合理的な根拠なく「TOB(株式公開買付)を実施する」という公表を行う行為が風説の流布に該当する可能性があると明記されました。その結果、そうした行為は確かに減少しました。
しかし一方で、「TOB をする」と直接発言するのは問題になると認識されるようになったものの、代わりに「ファンドをスポンサーにして非公開化しろ」「MBO(経営陣による買収)をしろ」といった提案を公表する手法が横行しています。これは株価への過剰な期待を生み出し、誤った投資判断を招く要因にもなっています。
このような状況を踏まえると、今後は一定の軌道修正が必要ではないかと考えています。」
上村「ちなみに上場企業の IR では、基本的には業績の話しか聞かれませんでした。会社の特性にもよるでしょうが、これはコードの想定する「エンゲージメント」といえるのでしょうか?もちろん、年金系の投資家の方など、業績についてはほとんど触れず、ビジネスモデルやガバナンス、企業文化(カルチャー)といった点だけに関心を持つ方もいらっしゃいましたが。」
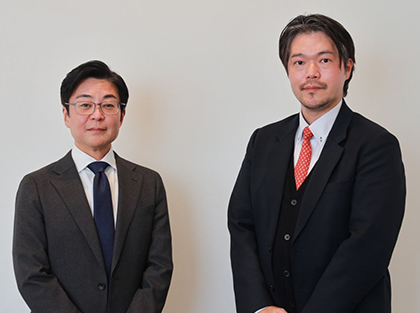
谷口氏「エンゲージメントに近いケースもありますが、一方で、次の決算の数字を聞き出すことに終始する投資家もおり、それは少し違うと感じています。ショートターミズム(短期志向)の問題の一つとして、フェア・ディスクロージャー・ルールの議論でも取り上げられましたが、そのあたりの在り方についても改めて考えるべきではないかと思っています。」
上村「上場企業の実務では非常に悩む点なので、整理されると投資家との対話促進につながると思います。
本日は、貴重なお話を様々頂戴しありがとうございます。最後に読者の皆様にメッセージをお願いできますか?役員会運営に関わる方が多くいらっしゃるかと思います。」
谷口氏「取締役会事務局というポジションは、コーポレートガバナンス改革の主役となり得る存在だと考えています。実際、金融庁をはじめとする各省庁の事務局が法令改正の際に主導的な役割を果たしているように、企業のガバナンスにおいても事務局が重要な役割を担っていると思います。その判断や対応が企業の意思決定に大きな影響を与えることは、間違いありません。
だからこそ、誇りと責任を持って業務に取り組んでいただきたいと思いますし、企業としても取締役会事務局の人材に対して適切な投資を行い、将来的に役員候補となるような人材を配置する流れが生まれることを期待しています。」
・取材を経て
谷口弁護士には、コーポレートガバナンスの実務に関わる方や関心をお持ちの方に、気づきを感じていただけるよう、コード策定時の思いやご自身のお考えについて踏み込んだお話していただきました。
さまざまな立場の関係者がいる中で、ソフトローとはいえ、コーポレートガバナンスコードを取りまとめるには相当な苦労がおありだったでしょう。それを成し遂げたからこその矜持をお話の中で随所に感じました。発表直前には経済団体から異論が出たものの、文言の調整を重ねることで理解を得るに至ったという経緯もあったそうです。とかくグローバル水準に追いつくことばかりが重視されがちですが、現状を踏まえつつ、目的に即して海外の先行事例を参考にしながら、コードとして何が最適かを追求し続ける姿勢には深い感銘を受けました。
一方で、コードは形式的で一律の対応を促進してしまう側面があるという懸念が何度も聞かれました。本来、制度は過度に踏み込みすぎるべきではなく、競争力は各企業の自主的な判断から生まれるべきという考えを強く感じました。
コーポレートガバナンス改革は、投資家に対し日本の上場企業全体への安心感をもたらす効果を発揮しているものの、本来の目的である中長期的な企業価値の向上は、ガバナンスの充実だけでは達成されず、各企業の実情に応じ適切な経営がなされることが求められます。
だからこそ、ガバナンスは実践のフェーズと位置づけていらっしゃるのでしょう。そして、取締役会の実効性を高めるためには、各社の役員はもちろん、事務局の果たす役割が極めて重要であることを強く認識しました。
谷口弁護士には長時間に渡りご対応いただき心より感謝を申し上げたいと存じます。
ガバナンスクラウド株式会社
代表取締役 上村はじめ