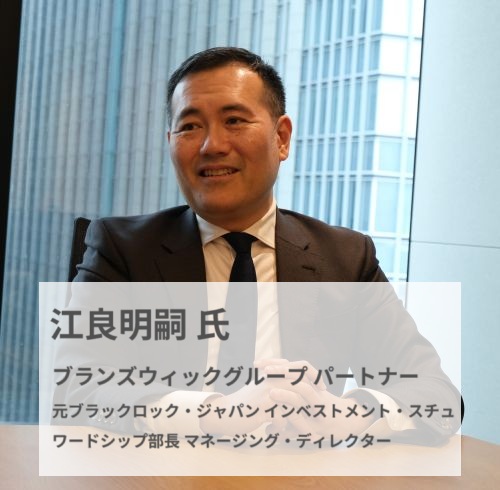日本では、企業の持続的成長と市場の透明性向上などの観点から、コーポレートガバナンスの充実が求められるようになりました。特に 2010年代以降、その動きは加速し、金融庁によるスチュワードシップ・コードやコーポレートガバナンス・コードの策定が注目を集めています。こうした改革の現場で実務に携わり、制度設計に関わったのが、TMI 総合法律事務所の弁護士・谷口氏です。
2012年と2022年の2回にわたり金融庁に出向し、単なる規制の監督にとどまらず、法改正や政策立案を通じて、日本の企業統治の未来を形作る業務に取り組みました。現在、TMI 総合法律事務所のパートナーとして、ガバナンス改革の最前線に立ち続け、この分野の専門家として重要な視点を提供しています。法律家の枠を超え、経営やファイナンスにも深い見識をお持ちの谷口氏に、ガバナンスコード策定主体の立場でお話を伺いました。
・ご経歴
2008年 3月 中央大学法学部法律学科卒業
2008年 4月 最高裁判所司法研修所入所
2009年 9月 東京弁護士会登録
TMI 総合法律事務所勤務
2012年 7月 金融庁総務企画局企業開示課勤務
2015年 4月 TMI 総合法律事務所復帰
2017年 1月 パートナー就任
2022年 7月 金融庁企画市場局企業開示課
企業統治改革推進管理官
2024年 4月 TMI 総合法律事務所復帰
・ご経歴
2008年 3月 中央大学法学部法律学科卒業
2008年 4月 最高裁判所司法研修所入所
2009年 9月 東京弁護士会登録
TMI 総合法律事務所勤務
2012年 7月 金融庁総務企画局企業開示課勤務
2015年 4月 TMI 総合法律事務所復帰
2017年 1月 パートナー就任
2022年 7月 金融庁企画市場局企業開示課
企業統治改革推進管理官
2024年 4月 TMI 総合法律事務所復帰

・インタビュアー
ガバナンスクラウド株式会社
代表取締役 上村はじめ
1999年センチュリー監査法人(現あずさ監査法人)入所。
監査、フィナンシャルアドバイザリーに従事 2004年(株)カカクコム入社。経営企画、IR、コーポレートガバナンス業務を担い2009年取締役としてコーポレート部門責任者を務める 2020年 コーポレートガバナンス・財務コンサルティング事業を開始。2021年 6月 ガバナンスクラウド(株)設立。
上場企業、海外企業含む多数の社外役員経験あり。公認会計士。
金融庁出向とコーポレートガバナンス改革との関り
上村「今日はお時間をいただきありがとうございます。よろしくお願いいたします。さて、まずは先生のご経歴についてお伺いします。金融庁へ出向された経緯についてご自身で希望されたのか、それとも何かきっかけがあったのでしょうか?」
谷口氏「私は 2009年 9月から TMI 総合法律事務所で弁護士として勤務を開始し、3年目の途中から金融庁に出向しました。弁護士として 2 年目から上場企業の M&A 案件を多く担当し、その業務に非常に魅力を感じました。
弁護士になる前から公開買付け規制(TOB 規制)に興味を持っており、実務で関わることでさらに深く研究したいと思うようになりました。公開買付け規制を管轄しているのが金融庁だと知り、同じ事務所から金融庁に出向した先輩がいたこともあり、次は自分が行きたいという強い意志を持って手を挙げ、無事に 2012年 7月に金融庁に出向することができました。」
上村「実際に金融庁に出向され、想定通りのお仕事に関わられましたか?」
谷口氏「初めは公開買付け規制の監督や改正に関わることを期待して金融庁に入りましたが、それ以上に多くの収穫がありました。金融庁はやる気があれば幅広い業務に携わることができる環境で、縦割りの意識があまり強くありません。そのおかげで、コーポレートガバナンス・コードやスチュワードシップ・コードの策定に関わり、さらに課徴金納付命令に関する訴訟や審判にも携わる機会を得ることができました。このように、想像以上に多様な経験を積めたことは私にとって大きな驚きでした。
弁護士事務所での勤務と比較すると、金融庁での稼働時間は短かったものの、仕事の緊張感は大きく、幹部への説明は一発勝負。通らなければやり直し、局長で却下されれば、課長からやり直しというプレッシャーの連続で、精神的・体力的にはかなり大変だった記憶があります。」

上村「最初に出向されたのは 2012年 7月ですが、その直後にスチュワードシップ・コードに関わられたんですね。当時、その先にあるコーポレートガバナンス・コードも視野に入れて動いていたと思いますが、プロジェクトとしての温度感はいかがでしたか?」
谷口氏「私が金融庁に出向して 1年ほど経った 2013年に、スチュワードシップ・コード策定の検討が始まりました。その頃、日本再興戦略が発表され、アベノミクスの三本の矢が話題になり、ガバナンス改革への関心が急速に高まりました。スチュワードシップ・コードの策定時点ではそこまで注目が集まっていませんでしたが、ソフトローという新たな試みで個人的にはとてもチャレンジングな取組みだと感じていました。
一方、2014年からは、コーポレートガバナンスコード策定に向けて、本格的な取り組みが始まり、市場からも注目が集まりました。課内も一丸となって、今まで関わりのなかった所管の人たちや会計士とも連携し、組織全体で取り組むという空気があり、金融庁にとって重要な政策として位置づけられていたことを実感しました。」
コーポレートガバナンスとは何か
上村「確かに、当時は『コーポレートガバナンス』という言葉が一般に広まっているわけではなく、主に法律や経営学の専門家が使っていた言葉だったかもしれませんね。私も、会計士試験の経営学の学習でその言葉を企業統治の意味として教わったことを覚えていますが、日常的に『コーポレートガバナンス』を使う機会はほとんどありませんでした。」
谷口氏「当時の『コーポレートガバナンス』のニュアンスは、どちらかというとコンプライアンスや内部統制の延長線上にあり、不祥事を防ぐための仕組みとして語られることが多かったように思います。本来の意味でのコーポレートガバナンスがどれほど浸透していたかと言うと、今でも完全に浸透しているとは言えませんが、当時は特に意識されていませんでした。
コーポレートガバナンスを一言で表すならば、『株主が経営者を監督するための仕組み』と言えるでしょう。これは最大公約数的な定義になるのではないか、というのが私の考えです。」
上村「そうした状況の中で、コードを作成するというのは政府主導のプロジェクトだったということですよね。その時点で、投資家からもそういった取り組みが必要だというプレッシャーはあったのでしょうか?」
谷口氏「確かに、海外の投資家を中心にそういった声は以前からあったものの、具体的なメリットが見えづらかった部分があったように思います。そのため、実現には時間がかかり、なかなか進展しなかったというのは理解できます。どんなメリットがあるのか、どう社会に影響を与えるのかという点を明確に示すことが重要だったのかもしれませんね。」
■日本のコーポレートガバナンス改革主な動き
| 年月 | 金融庁 | 東証 |
|---|---|---|
| 2014/2 | スチュワードシップ・コード策定 | |
| 2015/3 | コーポレートガバナンス・コード策定 | |
| 2017/5 | スチュワードシップ・コード改訂 | コーポレートガバナンス・コード改訂① |
| 2021/6 | 投資家と企業の対話ガイドライン改訂 | コーポレートガバナンス・コード改訂② |
| 2022/4 | 東証市場区分見直し | |
| 2023/3 | 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応要請 | |
| 2023/4 | コーポレートガバナンス改革の実質化に向けたアクション・プログラム | |
| 2024/6 | 同実践に向けたアクション・プログラム 2024 |
コーポレートガバナンス・コード策定に込めた思い
上村「コーポレートガバナンス・コードは『中長期的な企業価値の向上』を目的に策定されたということですが、その目的を設定された背景や意図についてお聞かせいただけますでしょうか?」
谷口氏「当時、私は専門官としてまだ若手であり、この目的設定に私が関与したものではありませんが、この目的には深い意図が込められているように感じます。まず、『企業価値の向上』という企業の成長性を重視した考え方は、伝統的なコーポレートガバナンスの考え方からすれば異例と思います。伝統的には、主に経営者を規律する仕組みという意味合いが強いように思いますが、『企業価値の向上』という目的設定はその枠を超えているように思います。
当時『失われた 20年』と言われていたように、日本企業の成長を促進することが喫緊の課題でした。アメリカの企業、特に GAFA などのグローバル企業が日本に生まれなかった理由の一つは、銀行主導のガバナンスが長らく根強く残っていたためとも言われます。この『デッドガバナンス』の下では企業の安定性が重視され、企業の成長性が重視されない傾向があります。これに対して、株主は企業の成長性とそれに伴うアップサイドを求める立場にありますので、株主主導のガバナンスに移行することで企業の成長性を促進することができるのではないかと考えたのだと思います。
バブル崩壊や持ち合い解消により、銀行主導のガバナンスが弱まり、株主主導のガバナンスに移行しやすいタイミングだったというのも一因としてあるでしょう。
この考え方は個人的にはとても面白いと思っていますし、理にかなったものと思いますが、本当にそううまくいくかは誰にも分かりません。最終的には歴史の審判の下で正しかったかどうか検証されることでしょう。
『中長期』という言葉が盛り込まれたのは、短期的な利益追求、いわゆるショートターミズムに対する懸念があり、そのため、長期的な視点が強調されたものと思います。また、年金基金などの長期的な投資を行う機関投資家の長期的リターンを向上させることで、日本経済全体の好循環を生じさせるという狙いもありました。」

上村「日本企業がグローバルで成長するために、コーポレートガバナンスが重要という考えがあったということですね。先生がこのコードの策定にあたって最も大事にされていたことは何でしょうか?」
谷口氏「私が策定したわけではないので偉そうなことは言えませんが、当時のチームとして特に意識されていたのは『このコードが誰に向けたものなのか』という点です。ひとつの目的としては企業に対するメッセージでもありますが、投資家へのメッセージとしての意味合いも大きいです。
海外の投資家にとって、日本の企業やマーケットがどのように成り立っているかがわからないことが多く、その不安を取り除くためにも、投資家が安心できる環境を作ることが重要でした。そのため、株主の権利を侵害しないことなど“当たり前のことでも書く”を徹底しながらコードが作成されていったことをよく覚えています。
また、英訳も入念に行われました。特に有識者会議のメンバーが一からチェックし、英語の原文を何度も修正してくれました。その結果、英語版は日本語の原文とは少し異なる部分もありましたが、それだけ海外投資家へのメッセージの強さを意識した結果だと思っています。」
上村「コーポレートガバナンス・コードの文面は非常にシンプルですが、その裏には多様な関係者の思いがあるのですね。コードが完成した際の達成感などその時の感想をお伺いできますか?」
谷口氏「このコードの策定に最も尽力したのは、当時の局長、課長をはじめとする金融庁職員の皆様ですので、最も大きな達成感を感じたのは彼らだと思います。その後、私も講話やセミナーを通じて、これまでの法律改正とは比べ物にならないほど注目を集めたことを感じました。特に『ガバナンスとは何か?』という基本的な問いが強く意識され、企業への影響が大きいと実感しました。
その後、弁護士に戻り企業の方々と話す機会が増えましたが、ガバナンスコードが導入されたことを伝えると、「面倒くさいものを作ってくれた」という冗談混じりの反応が返ってきました。現場での実施が大変だったことを実感しましたね。」
上村「そうですね、私も当時、上場企業の経営企画部門にいましたが、法律改正や通達がここまで企業に影響を与えることは他になかったと思います。全上場企業がガバナンスコード対応に追われ、各社間で『どこまで対応するべきか?』よく話しに上がりました。」
谷口氏「実際、私は弁護士としてコーポレートガバナンス・コード対応に関わることに消極的です。もちろんご相談はお受けしますが、例えば『こうすればコンプライになりますか?」といったご相談はなるべくお受けしないようにしています。その意味で、コードの意図や精神は伝えつつも、具体的なアドバイスは避けるようにしています。コードをどう実践すべきかは、経営を熟知されている役員の方々に考えていただくことが最適で、外部の弁護士があれこれ机上の論理を述べる事柄ではないと思っています。」
コーポレートガバナンス・コード改訂の背景
上村「コーポレートガバナンス・コードの策定を契機に、企業側が実情に応じて考えることが重要だということですね。コード発表後、世の中にどのような影響があったかについて、予想通りだったことと予想外だったことを教えていただけますか?」
谷口氏「そうですね、予想外のことが多かったというのが正直な印象です。良い意味では、予想以上に大きなインパクトを与えていた点がありましたが、一方で、どうしても『コンプライする』という方向に偏ってしまったことは悪い意味で意外でした。
CG コードに書かれていることを全て遵守する必要はなく、例えば『うちは従業員を最優先にする企業です』といった考え方であったとしても、それをエクスプレインすれば良いわけで、それでも、投資家がその企業に投資したいと思えば問題ないはずです。しかし、そうした思い切りのある企業はほとんど現れず、大半の企業が『とりあえずコンプライする』ことを選んでしまったのは、悪い意味での想定外の出来事でした。」
上村「その後、ガバナンスコードは現在までに 2 回改訂されていますが、最初から改訂は想定していたのでしょうか、それとも社会や世間の反応を受けて改定の必要性が生じ改訂されたのでしょうか?」
谷口氏「実はガバナンスコードが2回改訂されたことは予想外でした。最初にコードを策定する際、非常に多くのリソースを要したため、定期的に改訂が繰り返されるとは思っていませんでした。スチュワーシップコードには3年ごとの改訂が明記されていますが、ガバナンスコードにはそのような規定はありません。というのも、各界の利害関係が複雑に絡み合っており、調整が非常に難しいためです。
しかし、実際には3年後に改訂が行われ、その後も含め計2回改訂されています。これには、想定していた以上にコーポレートガバナンスの推進に関する議論が急速に進展したことを表していて、良い意味で予想外でした。あと東証の市場再編が行われたことも改訂の一因ですね。社会の変化に対応してガバナンスの推進が加速し、それに合わせてコードの改訂が行われたと言えるでしょう。」
上村「東証の市場改革は、グローバル投資家向けにプライム市場というわかりやすい市場を作ることに焦点を当てたものと思います。2021年の改訂もその一環で、プライム市場向けの原則が 10項目ほど追加されました。結果として、現在のコードは完成形に至っているとお考えですか?」
谷口氏「そうですね、完成形に近づいているとはいえ、まだ道のりは長いと感じています。投資家の方々はきっとそのように感じているでしょう。」
形式から実質への転換。ガバナンス改革の核心
上村「2022年 7月に企業統治改革推進管理官として復帰された時、ちょうど改革後の最初のアクションプログラムが発表されるタイミングでしたね。一度大きな改正を経て、2023年以降、アクションプログラムが 2年連続で発表されていますが、まずそのアクションプログラムのポイントについてお伺いしたいと思います。特に、コードの改訂ではなく、アクションプログラムという形で発表されたという点について、またそれが金融庁から出されたことについて、背景をお聞かせいただけますか?」
谷口氏「2022年から 2回目の出向になりますが、その際は専門官ではなく企業統治改革推進管理官として各施策に関わることができましたので、施策に私なりの考えも一部反映することができたと感じています。
当時、2回の改訂を経て『最低限の形式は整った』とする意見が多くありました。しかし一方で、企業が『とりあえずコンプライする』という傾向が強くなり、さらに形式を強化することが形骸化を招くのではないかという懸念も生まれました。金融庁内外からは、『コードの改訂だけでは真のガバナンス改革は実現できないのではないか』という意見も多く聞かれました。
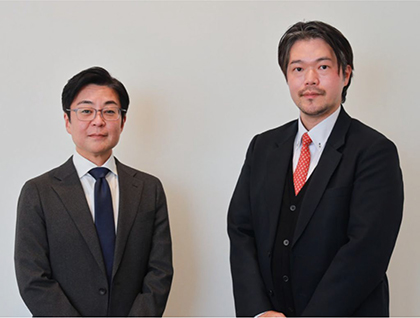
確かに、コーポレートガバナンス・コードは便利なツールであり、国会も通さずにただ内容を書けば企業がそれに対応をしてくれることが期待できます。しかし、形式的な対応だけでは、最終的な目的は達成できないと感じました。そこで、原点に立ち返り、中長期的な企業価値の向上を目指すために今何をすべきなのかということを考えるようになりました。
金融庁が実証研究なども公表していますが、いまだにコーポレートガバナンスの充実が企業価値の向上に直結するという確たる証拠はありません。したがって、コード改訂を続けることが本当に正しいのか、慎重に再考する必要があると感じました。そこで、改訂にとらわれず、形式よりも実質に注目すべきだという考えがアクションプログラムの最初の発想でした。この「形式から実質へ』というテーマは、フォローアップ会議の座長である神田先生からいただいた言葉でもあり、実質的な改革を目指すことに重点を置いています。つまり、コード改訂にこだわらず、現実的な課題に対して最適な方法を模索し、『改訂ありき』ではない議論を進めるというアプローチが、アクションプログラムの特徴です。
本来、2023年はスチュワードシップ・コードの改訂の年でしたが、エンゲージメントの促進という観点からは、改訂を実施する前に、まずは関連法制度、例えば大量保有報告制度などの見直しが必要だという議論がありました。その他にも、資本コストに関する東京証券取引所からの要請など、コード改訂以外の方法で様々な施策がとられています。」
上村「ありがとうございます。アクションプログラムは 23年と 24年で、タイトルが「実質化』から「実践』に、またガバナンスに特に関連する項目、「独立社外取締役の機能発揮」が「取締役会等の実効性向上』へと変わっています。この点、意識されたことはありますか?」
谷口氏「2023年は理想的な姿、つまり実質面としてこうあるべきだという視点が強かったのに対し、2024年はその理想を実現するために何をすべきかという実践面に焦点を当てています。具体的な施策として、2023 年には独立社外取締役の質の向上が重要だという認識が強調されましたが、2024年には質を高めるために何をすべきかという実践的なアプローチが強調されています。そのためには事務局の積極的な役割が不可欠だと考えています。これまでは事務局の重要性にあまり触れられていませんでしたが、現場でのブラッシュアップには事務局の役割を再認識し、そこに焦点を当てるべきだという視点を持つようになりました。」
上村「アクションプログラムにおいて、役員会事務局への役割期待はどのようなものでしょうか?」
谷口氏「社外取締役を活用するためのポイントとして、企業側からよく挙げられたのは、事前説明の時間、アジェンダ設定、そして事務局の取りまとめ役です。特に、事前説明で社外取締役から忌憚のない意見を引き出し、その情報を経営陣に伝えることが重要で、事務局の役割が大きいです。事務局は単なる事務作業にとどまらず、優れたガバナンスを持つ企業では経営に対して重要な影響力を持つと考えています。」
上村「社外役員への説明と調整は事務局の重要な役割ですね。議案だけではなく、会社の現状や方向性への理解がなければ、執行側の意図が伝わらないこともあります。こうした役割が社内で十分に認識されず、人手不足やシステム的なサポートが得られず、苦労している事務局も多いです。
弊社が提供する『Governance Cloud』は、役員が必要な情報にいつでもアクセスできる環境を整えることで、事務局の負担を抑えつつ、審議活性化により取締役会の実効性を高めることを目指しています。
実際、IT ツールの活用は、取締役会の実効性に寄与するというアンケート結果もありますが、コードやアクションプログラムの検討にあたり、IT ツールの活用について議論はありますか?」
谷口氏「おっしゃる通り、ガバナンスにはしっかりとしたコストをかけるべきだという考えには賛同します。人材の確保や IT ツールの導入など、ガバナンスを整えるためには短期的に安価で済ませることは難しく、そのためのコストや人員配置、必要な投資をしっかりと考慮する必要があります。フォローアップ会議においてもそのような意見がありました。今後金融庁が発表を予定している好事例集が『ここまで大変なことをやっているのか』と実感できる内容になっていることで、それを見た方々が『もっと人材の確保や IT ツールの導入に投資しなければならない』と考えるきっかけになれば理想的です。事務局の方々だけでなく、経営者にも目を通してもらい、『これだけ事務局が対応しているんだ』と認識してもらうことが、ガバナンスの重要性をより一層理解してもらう助けになると思います。」